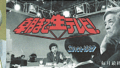釧路湿原で進むメガソーラー建設問題
先月,トランプ大統領は国連での演説で「気候変動は史上最大の詐欺だ」と述べ,石炭を「クリーンエネルギー」と位置づけました。また,エネルギー安全保障の強化を理由に,石炭火力発電の拡大を指示しました。「地球温暖化対策・温室効果ガス」の推進の背景には,当初EUがトヨタのガソリン車対策として電気自動車への転換を進めた経緯もあったと指摘されています。
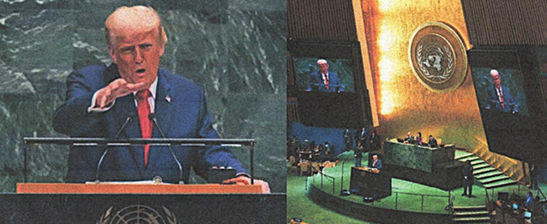
一方,日本では北海道の釧路湿原で進められているメガソーラー建設が大きな問題となっています。登山家の野口健氏をはじめ,多くの専門家や市民が強く反対の声を上げています。釧路湿原はラムサール条約に登録された国際的にも貴重な自然環境で,国立公園として保護されています。
この湿原は約六千年という長い年月をかけて形成されたものであり,盛土による開発で一度失われた自然を元に戻すことは不可能とされています。さらに,事業者による違法な造成行為も確認されており,厳しい批判が集まっています。

・現在は撤去された鹿児島市宮之浦町牟礼岡の風力発電
太陽光発電は,温室効果ガスを排出しない再生可能エネルギーとして高く評価されてきました。国連も(中国の影響を受けながら)その普及を後押ししてきました。しかし日本では,「2050年カーボンニュートラル」や「温室効果ガス46%削減」といった目標が,現在では欧米を含め世界的に形骸化されているのが現状です。
それにもかかわらず,日本では労働組合や教職員の運動とともに,SDGs(持続可能な開発目標)の理念である「誰一人取り残さない社会」の実現を目指す取り組みが進められています。貧困や飢餓,教育,ジェンダー平等,気候変動など,さまざまな目標が掲げられ,学校教育の中でも教えられています。しかし,地方経済の状況を見ると,これらの取り組みの中身よりも補助金に依存した政策運営に偏っているのが実情です。

・肝付町国見山の風力発電
EUがすでに方針を転換しているにもかかわらず,日本が政策を見直さない背景には,官僚や政治家の利権構造が温存されているとの指摘もあります。巨額の税金が投入され続ける中で,その延長線上にあるのが,釧路湿原の自然を破壊するメガソーラー建設だと,専門家たちは強い警鐘を鳴らしています。

・吉田町のソーラーパネル
ノーモア・メガソーラー宣言
北海道の釧路湿原で進められているメガソーラー建設は,平坦な地形と長い日照時間を理由に,事業者から「最適な設置場所」とされています。
しかし,この地域は特別天然記念物のタンチョウやオジロワシなど,希少な生き物が生息する非常に重要な自然環境です。そのため,開発によって生態系に深刻な影響が及ぶことが強く懸念されています。
こうした状況を受けて,釧路市は鶴間市長のもとで「ノーモア・メガソーラー宣言」を掲げ,自然環境を守る姿勢を明確にしました。地元住民の間でも反対の声が高まっており,建設計画に対する反発が強まっています。登山家の野口健氏もまた,森林伐採や地形の改変による環境破壊を深刻な問題として訴え,オンライン署名を通じてメガソーラー建設の中止を求めています。

・ タンチョウやオジロワシ
鹿児島の未来を支える鍵
鹿児島県は,「鹿児島市」「屋久島」「奄美・徳之島」という三つの世界遺産を有する,日本で唯一の県です。観光を基盤とする「観光立県」として発展を続けるためにも,自然環境の保全は極めて重要な課題です。
しかし近年,この貴重な自然景観が急速に失われつつあります。過去十年を見ても,風力発電所が景勝地の眺望を遮り,山の斜面には広大な太陽光パネルが設置され,自然環境や景観を壊しています。再生可能エネルギーという名のもとで進む開発が,皮肉にも環境破壊を引き起こしているのです。
鹿児島が観光立県として持続的に発展していくためには,エネルギー政策と環境保全のバランスを真剣に考える必要があります。豊かな自然と美しい景観を守ることこそが,鹿児島の未来を支える最大の鍵であると思います。

・ 屋久島及び奄美・徳之島の世界遺産
森林環境税
温室効果ガス削減の取り組みについては,例えば約150兆円という莫大な費用を投じたとしても,世界の平均気温をわずか0.006度下げる程度の効果しかないとされています。(これを単純計算すると,4人家族で600万円を地球環境のために支出することと同じことになります。)
こうした世界情勢の中で,なぜ日本だけが過度な負担を背負ってまで対策を進めなければならないのか,極めて不合理だと言わざるを得ません。国際社会の中で「NOと言えない日本人」のままで,他国の方針に従い続ける日本の姿勢は,戦後から今に至るまで,ほとんど変わっていないように思われます。
世界最大のCO₂排出国である中国をはじめ,2位のアメリカ,3位のインド,4位のロシアといった主要国はいずれも対策を講じていません。そのような中で,日本だけが多額の税金を投入し続けるのは,国家の方針として大きな問題と言わざるを得ません。日本のことを真剣に考える政治家・官僚・ジャーナリストはいないのでしょうか。
また,国民一人あたり年額1,000円が徴収される「森林環境税」は,本来,「森林の保全」を目的として地方自治体に配分されるものです。しかし現実には,その森林が伐採され,メガソーラー建設が進められているという,矛盾した事態が各地で起きています。

・吉田町のソーラーパネル
こうした開発の背景には,「中国資本」の参入や「国の補助金制度」への過度の依存があります。鹿児島県でも,環境や観光資源を犠牲にしてまで建設業界の利益を優先する構図が見られます。先日,久しぶりに吉野や吉田の山を訪れましたが,数年前と比べて急増したソーラーパネルの光景に大変驚かされました。

日本のエネルギーを考える
2025年10月26日に放送された「そこまで言って委員会」では,エネルギー政策がテーマとして取り上げられました。番組の中で,総裁選に立候補した高市氏は,エネルギー政策の柱として「資源安全保障の強化」を掲げ,「化石燃料への依存によって国富を流出させたり,資源国に頭を下げるような外交を終わらせたい」と強調しました。私はこの発言に強く共感し,久しぶりに頼もしいリーダーが現れたと感じました。
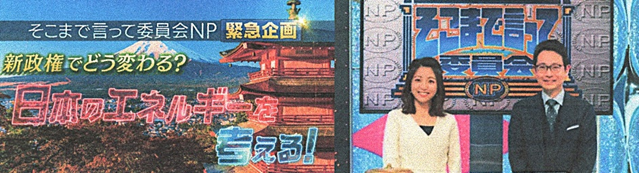
高市総理はまた,日本のエネルギー自給率を引き上げる強い決意を示すとともに,「これ以上,美しい国土を外国製(中国製)の太陽光パネルで覆い尽くすことには断固反対である」と明言しました。この言葉には,国を守る責任ある姿勢が感じられ,非常に感動しました。
さらに,耐用年数を迎える初期型の大型太陽光パネルの安全な廃棄問題にも触れ,現行政策の課題を的確に指摘していました。高市内閣の誕生により,日本のエネルギー政策は大きな転換期を迎えることになると感じます。
近年,鹿児島県内では風力発電や太陽光パネルの設置が急速に増えています。この現状を見ると,もはや看過できない深刻な故郷の環境問題であると強く感じます。
※ 次回に続く