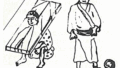勤務中に胸が苦しくなったことをきっかけに,たばこをやめてから25年近くになります。ヘビースモーカーではありませんでしたが,学生時代からたばこを吸っていました。教員時代も,禁煙してはまた吸うということを繰り返していました。
学生時代の私の友人は殆どタバコを吸っており,ハイライトやピース派の友人が多く,私には少しきつかったので,セブンスターを吸っていました。その頃は流行りもあり,エリック・クラプトンがラークを吸っていると知ると,しばらくはラークなどの「洋モク」煙草を吸ったり,お金が入るとすこし贅沢して高い煙草を買ったりして楽しんでいました。
就職してからは,ニコチンやタールの少ないたばこにして,健康に気を使っていたつもりでした。その後は,さらに健康を意識して,1ミリグラムのたばこだけを吸うようになりました。まあタバコ自体が健康に悪いことは分かっていても習慣になると中々止めれることができなかったのです。

ここで,たばこに関するエピソードをいくつか紹介します。
◆ その1「キセル」
たばこのことで初めて記憶に残っているのは,前回「初めての冒険」で紹介した仲良しお爺ちゃんの家でのことです。そのお爺ちゃんはいつもキセルでたばこを美味しそうに吸っていました。父は煙草をそのまま吸っていたのに,あるとき,わざわざ巻紙を破って中のたばこ葉を取り出し,それをキセルに詰めて吸っていたのを見て不思議に思いました。どうしてもキセルで吸いたかったのだと思っていました。家にあった5〜6個のたばこの箱から巻紙を破って中から刻み葉を取り出す手伝いをしたことがあり,なぜか印象に残っていました。
家に帰ってから,私はお爺ちゃんにプレゼントしようと父が買い貯めていた「しんせい」をばらしていると学校から帰ってきた父に怒られたことがありました。お爺ちゃんのことを話すと,父もキセルに詰めて吸っていましたが,あまり美味しそうな顔ではありませんでした。


父の吸っていた「しんせい」は40円でした。いつもお使いに行きおつりの10円がもらえたので覚えています。
◆ その2「学校での喫煙について」
鹿児島は,かつて日本を代表する葉タバコの産地でした。「花は霧島,たばこは国分」と『おはら節』にも歌われているように,国分のたばこは,藩政時代から全国的に有名な特産品でした。その後も,たばこが主要な農作物の一つとして県内各地に葉タバコの畑が広がっていました。

・学校横の葉タバコ畑
公共施設施設内での禁煙
平成時代に入り,勤務していた学校の校長先生が「職員朝会や会議中の喫煙をやめましょう」と提案しました。ちょうど妊娠している先生もいたので,反対意見は出ませんでしたが,喫煙していた先生たちにとっては驚きだったようです。私自身も禁煙してから気づいたのですが,隣でたばこを吸われると煙が漂ってきて,むせるのです。中には教室でたばこを吸っていた先生もいたほどで,今では考えられないような話です。
その後,公共施設施設内での禁煙の流れが強まり,教頭時代にPTA総会の場で「校内禁煙」について説明したところ,保護者で農協理事の方から「皆の前でそういう話はしないでほしい。本校にも10軒以上葉タバコ農家がいるんですよ。」と言われたことがありました。今では公共施設での禁煙は当たり前になりましたが,その少し前まで職員室で先生たちが日常的にたばこを吸っていたので,子どもたちのことを考えると当然だと思いました。令和元年7月から改正法の一部が施行され,学校や病院などが「敷地内禁煙」になりました。

・夏場の収穫作業の様子
「たばこは百害あって一利なし,直ぐに止めるべし」と年配の養護教諭が言うと,何人かの愛煙家の先生方と口論になったこともありました。今では,公共施設施設内で喫煙できないので,学校の裏門や周辺で吸っている先生方を見かけると考えさせられます。愛煙家の権利はないのか。受動喫煙を言うのであれば,屋上を開放してもいいのではと主張する先生方もいたようです。
■指宿はたばこの発祥地

・ 山川の豪商・河野家(藩の貿易商人)の墓に刻まれた「煙草盆とキセル」。あの世でも大好きな指宿葉を吸うために山川石に彫った墓(指宿市山川の旧正龍寺石群)

・河野家の墓石
薩隅煙草録と三國名勝図絵に書かれた指宿葉
| 1 薩隅煙草録 1543年,たばこは鉄砲と一緒に種子島に伝えられたそうです。そして指宿は日本のたばこ発祥の地とされています。たばこの発祥地としては,長崎などいくつかの場所が知られています。たばこの栽培について書かれた『薩隅煙草録(えんそうろく)』には,「慶長の初めごろにその種を手に入れて,指宿の里に植えたのが,日本のたばこ栽培の始まりである」と記されています。 このため,指宿は日本のたばこ栽培の発祥地とされているのです。かつては,指宿で作られたたばこは「指宿葉(いぶすきば)」と呼ばれていました。もし指宿で慶長初年(1596)に栽培が始まっていたとすれば,日本で一番早いということになります。 2 三國名勝図絵 また,三國名勝圖會の指宿の「煙艸(煙草)」項に, 『煙草(たばこ)は,いくつかの村で生産されていますが,特に十二町(村)で作られるものが最上とされています。これは砂地で育てられているからのようです。 この村の煙草が他より優れている理由は,一晩中吸って吹かしても舌が痛くならないこと,煙の量が多いこと,火のつきやすさが良いことなどです。そのため世間の人々の間では,「揖宿の煙草は,濡れた指でつかんでもよく火がつく」と言われるほどです。 また,風味も非常に良い上に,値段もそれほど高くないため,中流階級の家庭では特に好まれていたのです。一般に薩摩藩の煙草の名産地は,国分や出水などとされていますが,この村の人々は,村の煙草に誇りを持っており,「国分に次ぎに優れている」と言っています。とあり,当時国分煙草は高級品で,指宿煙草は品質(味・香・火の付き)もよく安いのでいいです。』(現代語訳) と,三国名勝図絵では紹介しています。 また,伊能隊が薩摩にやって来たとき,藩の役人が「泡盛」と「国分煙草」を手土産に,打ち合わせに訪れたそうです。伊能隊では飲酒が厳しく禁じられ,飲んだ場合は解雇される決まりだったため,泡盛は一旦江戸へ送られました。一方,煙草は隊員全員に配られ大変喜ばれたそうです。当時の泡盛や国分煙草は,全国的にも高級品として知られていたのです。 |