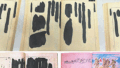本日,8月16日は,亡き義父が生まれてちょうど100年目となる日です。

・旧鹿児島県庁舎本館 竣工1925年(大正14年)
義父は,1925年(大正14年)8月16日の生まれです。同じ年に生まれた著名人には,作家の三島由紀夫氏,落語家の林家三平氏,脚本家の橋田壽賀子氏,哲学者の梅原猛氏などがいます。この世代が生まれたのは,まさに激動の時代でした。戦前・戦中・戦後という日本の大きな転換期を,思春期から青春期という最も多感な時期を過ごしていました。
日中戦争が始まり,戦争はやがて日常となっていきます。学校生活もままならず,学徒出陣や勤労動員,そして戦場へと動員されていきました。青春を謳歌する間もなく,彼らは戦争に勝つことを第一に,日々の暮らしに必死で向き合っていったのです。
平和の尊さを身をもって刻んでいった世代だからこそ,それぞれの分野を開拓し,時代を象徴するような人物が多く育っていったのです。明るい未来を諦めることなく,戦後日本の土台を築き,現代へとつながる礎を作ってくださった人たちです。この世代の人に思いを馳せるたびに,深い敬意と感謝の念を抱かずにはいられません。
一方,1925年3月には,東京で日本初のラジオ放送が始まりました。新しいメディアと言われ,新しい日本とその文化の幕開けに,国民は大きな期待を抱いたことでしょう。当時の人口はおよそ6000万人で現在の半分でした。(現在1億2,330万人)。
今の日本を作った世代
父が生まれてからの二十年間は,国全体が戦争に突入し,敗戦を経て,焼け野原からの復興に向けて歩み始めた,まさに激動の時代でした。民主主義の確立に向けて,人々は混乱の中を懸命に生き抜いていったのです。彼らが,現在の平和で豊かな日本の礎を築き上げ,世界第二位の経済大国へと発展させてきたのです。
その後アメリカとの貿易赤字に伴う日本叩きや経済政策の失敗,増税などで日本経済は失速していきました。その陰で官僚たち,政治家たち,雇われ経営者たちのご都合主義の失策が更なる遠因となり回復し難い状況にまで陥ったと,私は考えています。
年金問題
そして近年,年金問題では「少ない若者が多くの高齢者を支えているのでやがてパンクする」といった財務省の口車に乗って,高齢者が一方的に批判の的となるような風潮を高め,若者たちの不満を煽るだけでなくこっそり年金を減額を画策しているのです。「公的年金の100年安心」は一体何処に行ったのでしょうか?低賃金に悩む若い世代の不満を高齢者に向けるという,江戸時代から伝わる古い手「耳障りの言い事や不満を他にそらす手法」を今の官僚や政治家,マスコミが凝りもせずやっているのです。
その上,不満をそらされた若者たちも,結果的に同じ理屈で将来の自分たちの年金も減らされるのです。まともな国にするためには,まず還付金や補助金といった目先の甘い言葉に惑わされず,それに繋がる官公庁や政治家の既得権益を減らしながら年金システムを変え,少しずつ西欧諸国並みの年金制度に変換していけばいいのです。〖とは言ってもやはりお金の匂いを嗅ぎつけ,白アリのこどく既得権者が忍び寄ってくれば同じか…〗
更にこの世代は,本来受け取るべき水準よりも「はるかに低い賃金」で,命を削るような努力を重ねてきたのです。それを原資として社会インフラ等を整えていき,短い期間で戦後復興が叶ったのです。更に子どもを成人させ,なんとか老後のために蓄えた預貯金さえも狙われているのです。この世代に対して,今のような扱いをする前にやることがあるはずです。
「官僚や政治たちの失策の穴埋めに取れるところから取るやり方」に強い違和感を覚えずにはいられません。ゼロからの復興を生き抜いてきた人々に敬意と感謝の意を表せなければ,次は同じように若い世代のあなたも狙われますよ。(ド~ン!)By喪黒福造

波乱万丈な義父の人生
父が亡くなって既に20年が経ちますが,改めて考えてみると,大正14年(1925)の生まれですので,1歳の大正15年が昭和元年であることから,父は昭和の年号と自身の年齢が一致する人生を歩みました。例えば,昭和16年12月8日,太平洋戦争が勃発したときは16歳。昭和20年8月15日の終戦のときは20歳であり,その翌日には21歳の誕生日を迎え,昭和が終わる年は64歳ということになります。このように,昭和の年号と年齢が重なることで,義父の人生の節目を非常に分かりやすく感じることができます。
10代は軍事訓練に明け暮れ,17歳から20歳までは駆逐艦涼月に乗務し,戦争のまっただ中に身を置いておりました。終戦後の20代は,故郷の役場に勤務し,戦火で焼け野原となった町の復興作業に従事していました。
回りの人に慕われていた義父
その後は自衛隊に入り,佐世保や鹿屋などで生活を送りました。そして50歳で定年を迎えたあとも,再び役場に戻り,「区画整理事業」の担当者として多くの調整業務に携わる日々を送りました。代々受け継がれてきた土地の一部を手放すことに,住民からの強い反発があったこともあり,父はその調整役として,日々遅くまで住民と真摯に向き合っていました。同僚たちからは,「あの役目は,義父にしか務まらなかった」とまで言われていたそうです。

・ 海軍鹿屋基地
並行して,地域の人たちからも信頼され,公民館長を連続20年以上にわたって務め,その間地域活動にも尽力しました。自衛隊退職後には文化刺繍という新たな趣味に出会い,青春を取り戻すかのように,多くの繊細な作品を残しました。
父の人生を振り返ると,青春と呼べる時期は戦争に費やされ,その後も国のため,地域のために働き続けた,まさに激動の人生でした。また,長男として両親と7人の弟や妹の面倒を見ながら,結婚後は3人の子育て,最後は病に伏した妻の看病と目まぐるしい人生を貫いた人でした。孫も4人授かり幸せな人生だったでしょう。いつもニコニコと笑顔を絶やさない優しい人でした。
ありがとうございました。