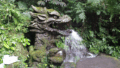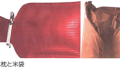母は,昔のことを語るのが好きな人でした。日記もこまめに残しており,晩年には自分史を綴っていましたのでそれを基に記します。
戦後80年という節目を迎え,テレビドラマやドキュメンタリー番組などで,ヤミ市の情景が描かれるのを目にする機会が増えています。そうした映像を見ていると,母が話してくれた数々の戦後の話がふと思い出されます。

・ 昭和30年代の西駅(鹿児島中央駅)
西駅のヤミ市
鹿児島市は,アメリカ軍による焼夷弾爆撃によって,街の大部分が焼け野原となっていました。そのような混乱の中でも,人々の暮らしは止まることなく,天文館や西鹿児島駅前をはじめ,市内のいたるところに「ヤミ市」が出現していました。
なお,西駅のヤミ市もバラック作りの飲食店や露店が立ち並び,終日多くの人で賑わい活気に満ちていました。戦災復興事業により昭和25年4月に駅舎が完成するまでは,闇市が盛んに開かれていたそうです。その後は規制が厳しくなり,闇市の数も次第に減少していったようです。
一口に「ヤミ市」と言っても,戦中と戦後ではその様相は大きく異なっています。戦中は厳しい統制のもとで秘密裏に行われていたのに対し,戦後は,生活のための手段として,駅近くの空き地で普通に行われていたのです。
戦後,母は教員を辞めた後の2年間,親戚が行っていたヤミ市で働き始め,日々の糧を得ていました。6人の幼いきょうだいたちを食べさせ,家族が生き延びるために必死で働いていたのです。教員を辞めた一番の理由が給料が少なく,高騰した食料品などが購入できなかったからでした。
今の私たちには想像もつかないほどの苦労があったと思います。米や野菜の買い出しに奔走し,時にはより高値で売れる福岡や熊本など県外にまで出かけて,売り歩いたこともあったのでした。
当時の母の姿を思い浮かべながら,戦後,同じように混乱期を生き抜いた人たちのたくましさと,家族の絆の深さに,今を生きる者として改めて感謝の気持ちが湧きあがります。
フリーマーケット
昭和21年1月,鹿児島市では,西駅や天文館,新上橋,海岸通りなど市内5か所にフリーマーケットを設置することになりました。戦後の混乱期にあって,少しでも市民の生活を支えようという動きだったのでしょう。その後,物価を抑える数々の制度が導入され,ヤミ取引の取り締まりも強化されましたが,深刻な食料品不足は解消されず,依然として高値での取引が続いていました。
鹿児島市のヤミ市では,近郊の農家の方々が直接販売することも多く,薩摩半島の農村部も,食料品の不足が続いていました。川辺の山間部を訪れても手ぶらで帰ることが多かったようです。そこで母は,遠く肝属・曽於地区まで買い出しに出かけていたそうです。
最初のうちは,戦前から鹿屋で商店を営んでいた叔父のつてを頼り,古くから取り引きのあった農家を回っていました。しかし,米を分けてもらうことは難しく,せいぜい野菜を少し分けてもらえる程度だったそうです。
なお,叔父は戦前から西駅や鹿屋市内で小規模な店舗(ストアー)を経営しており,従業員も数十人雇っていたそうです。従業員の雇用を守るためヤミ市での販売を行っていたということですが,当時は家族の生活を守るため公務員や会社勤めの人なども行っていたようです。
やがて母は,「自分で新しく仕入れ先を開拓するしかない」と考え,曽於郡野方や高隈山の串良川沿いの農家を訪ね歩き,ようやく米や食糧を手に入れられるようになったそうです。
銀シャリのお握り
米や野菜が少しずつ手に入るようになると,そのまま売るよりも,おにぎりや弁当にして販売する方が高収入に繋がりました。特に戦地からの引き揚げ者たちにとって,銀シャリ(貴重な白米だけの白いご飯)など温かい食事は,夢にまでみたありがたい食べ物だったのでしょう。母の作ったお握りは飛ぶように売れ,1日で教師時代の月給の5倍から10倍もの利益が出ていたそうです。
※ 教員時代の母の給与は,月額40円から翌年は50円に上がるなど,物価を少しは考慮していました。しかし,白米一升の値段にも満たず,とても家族を養える額ではなかったのです。

この話を初めて聞いたとき,戦後の混乱と飢えの中でただ生き延びるだけではなく,工夫と努力で家族を支えようとした母の強さに頭が下がる思いでした。また,戦前から戦後を生き抜いてきたこの世代の人たちが,今の日本の礎を作ってきたことは間違いないと改めて思うのです。
戦後直ぐに教員として働き始めても,僅かな給料のほとんどを家に入れ,兄弟姉妹の面倒も見なければいけない。毎日が忙しく,仕事の遣り甲斐や達成感など感じる余裕もなかったそうです。また,当時の務めていた女性の多くが,男性が復員するとその人のために仕事を辞めることが暗黙の了解だったことも聞きました。
そのようなことで,教員を辞めて本格的に西駅近くの商店を営む叔父の手伝いをすることになったそうです。そこは,いわゆるヤミ商売もしていて,そこで手伝いをすると,高額なアルバイト料と,配給では手に入らない白い米や野菜,味噌などがもらえたのです。
ヤミ市での不法占拠
当時,県内には特攻隊の飛行場建設(結局,使われなかった特攻飛行場・関連施設もありました)のために,戦時中まで日本の統治下にあった朝鮮から多くの人々が働きに来ており,彼らはやがて県内の数カ所に集落を形成するようになりました。戦後になると,その一部の人たちがヤミ市を営むため,県内の各地から集まり,土地を不法に占拠するという事態が起こっていたのです。もちろん日本人も大勢いたのですが,朝鮮系の人たちは徒党を組み,集団でやって来るので話し合いが出来なかったそうです。終戦直後はそのような混沌とした時代だったのです。
母の叔父も自分の土地を不法に占拠されていました。警察などに相談していたものの,戦後の混乱期ということもあり,なかなか解決されませんでした。その内何件かは刃傷沙汰にまで発展したのでした。母が商売の手伝いを始めた頃は,やむを得ず別の土地を借りて営業を始めていたようです。数年後,その土地は返されましたが,こうした出来事は当時全国のヤミ市では,珍しいことではなかったようです。
高隈山の夕日はつるべ落とし

・山の稜線を浮かび上がらせる高隈の夕日
秋口の高隈は西にそびえ立つ高隈山の影響で,鹿屋市街地より陽が落ちるのが早く,買い付けが遅くなると鹿屋の旅館には夜遅く着くことも多かったようです。夕日で山が茜に染まる頃,その山容はまるで「天にはさみを入れた」ようにくっきりと浮かび上がり,空と山の境を裂いているようでした。
日が沈む前に鹿屋に着かなくて,辺りは暗い闇になり,また砂利道のデコボコはとにかく歩きにくく,何回も転んだことがありました。赤々とした太陽が山に沈むまで出来るだけ距離を稼がなくてはなりません。夕日が山肌にかかると,「秋の日はつるべ落とし」と言われるように,ほんの一瞬で暗闇が這い寄ってくるのです。20代の女一人旅の不安と怖さからなのか,涙がこぼれ落ちてきたことが何回もあったそうです。

高隈の農家で購入した野菜と米の包みを背に,山道を急いで下ると額には汗がにじみ,肩にはバックの重さで紐が食い込んできました。鹿屋までの道すがら,何度も同じ風景を見てきたはずなのに,夕暮れ時はなぜか心がざわめいていたそうです。
米不足から菜種油へ
秋も暮れると,仕入れも徐々に少なくなり,農家の蔵には余り食べ物は残っていなかったのです。なんとか購入できても芋は細く,米はもみ米ですが直ぐに二級米と分かる細かなものばかりでした。叔父の店に運び込んでも,大した収入にはならないだろうと,一抹の不安がため息と共に気持ちまでも沈めるのです。それでも,足を止めるわけにはいかず,ただ夜の山道を黙々と歩くしかなかったのでした。月明りがあれば,まだ歩きやすいのですが,曇りの日は懐中電灯で足元を照らしながら,駆け足で宿に帰って行ったそうです。

ある時は夜中に宿にたどり着き,玄関を叩いてようやく主人が起きてきて,中に入れたこともあったそうです。また,母はいつも宿の主人から新しい情報を聞いて次の予定を決めていました。宿の主人は,宿泊者や取引業者などから多くの情報を得ており,同業者よりもいち早く情報を知ることで販路を開拓できるのです。そのときは,串良方面で菜種油を生産している農家が数軒あることを教えていただき,米以外の品物を新たに仕入れることができたそうです。

次回は,福岡での出来事です。