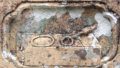これまで勤務した学校の校庭には,楠(くすのき),フェニックス,コマユミ,もみの木など,たくさんの樹木がありました。その中の樹木に「ぼくの木・わたしの木」と書かれた樹木札が下がっている学校がありました。これは,卒業生が入学したときに,それぞれが自分の木を選んで観察するためのものです。残念なことは,その学年が最後でそれ以降取組んでいないということでした。ですから他の学年の子どもたちは,校内にあるたくさんの樹木の名前を知らなかったのです。雑草園や岩石園などを作ったり,樹木札をつけたりしても,関心がなければ目にとまらないようです。花も同じで,まず名前を知り,色や形,匂いを覚えていくことで,自然に関心を持ち,大切にする気持ちが育ちます。
確かに学校の指導内容や先生方の指導時間の確保を考えると,このような取組を続けていくのは無理があるのだろうと思われます。ゆとり教育の「創意の時間」に生まれた多くの特色ある教育活動がなくなっていきました。

子どもたちは,その木を1年間或いは6年間かけて観察し,スケッチしたり,四季折々の変化をノートに記録したりするのです。二十四節気(特に立春・春分・夏至・立冬)に校内の散策をとおして定期的に観察を続けていく取組です。春には新芽が出て,夏には青々とした葉が茂り,秋には紅葉し,冬には葉を落とす。樹木や草花は,自然のサイクルを目に見える形で,四季の衣替えを教えてくれます。

・私は花粉症で近づけませんでした。
たとえば,秋口になると,体育館の前にある金木犀(きんもくせい)が甘い香りを漂わせています。その後,イチョウの葉が黄色く色づき,やがて地面を黄色いじゅうたんのように覆うでしょう。その上で子どもたちは遊び,自然と触れ合いながら季節を五感を通じて感じていきます。

子どもの感性を育む
かつて,子どもの日記に「学校からの帰り道,土手を見ていたら,ツワブキの花が話しかけてくれました。」とありました。そんなふうに自然と会話できる感性は,これからの時代にこそ大切なのではないでしょうか。この子はやがて文学の世界に入り,大手出版社が発行する外国絵本の翻訳者となりました。確かに薄暗い土手に咲くツワブキの花は精一杯自己主張して虫たちに訴えかけていますね。そこに気づくための取組が「ぼくの木・わたしの木」なのです。

けれど,もし花の名前を知らなければ,それは目に入っていても気づかれず,季節の変化も「暑い・寒い」だけで感じるようになってしまうかもしれません。
自然との触れ合いから得られるもの
県内の学校の多くは自然に恵まれた環境の中にあります。それでも,子どもたちに自然とふれあう体験をさせなければ,都会の中にいるのと変わらない生活になってしまいます。特別な場所や行事でなくても,日々の登下校の中で,自然と出会い,感じることはたくさんあります。
雨の日には,傘の中から見る景色があります。風の強い日は,寒さの中で見える光景があります。けれど,親が車で学校まで送り迎えしてしまえば,そういった体験や,体力,そして感性を育てるチャンスまでも奪ってしまうのです。
最近,「子どもが感動しなくなった」と言われることがあります。でも,本当は,私たち大人が自然との触れ合いの機会を減らしてしまっているのかもしれません。自然との日々のふれあいの中で,子どもたちはたくさんのことを感じ,学びます。そして,その体験がやがて子どもたち一人ひとりの個性として,きれいな花を咲かせていくのだと思います。