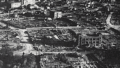先日,ドライブ中にラジオから,本田路津子さんの「ドナドナ」が聴こえてきました。久しぶりに耳にするこの歌は,今から60年近く前,NHKの『みんなのうた』で流れていた懐かしい曲です。この曲は何人もの歌手が歌っていますが,初めてヒットさせた歌手が岸洋子さんだったと思います。

当時は学校でもドナドナが流行しており,友人の家にあったシングル盤のレコードを一緒に聴いては,歌詞を書き出して二人で歌ったものです。歌詞の意味について深く考えることはありませんでしたが,メロディーが好きで,気がつけばよく口ずさんでいました。しかし,この歌の歌詞の意味を知ったのは,教員になってからのことです。教科書会社の音楽指導書に,歌詞の解釈とともに背景の説明が添えられており,そこで初めて知りました。
その頃,教職二年目で作文指導で行き詰まっていた時でした。「この詩のような感動的な作文ができないだろうか」と,脳裏をかすめたことがありました。
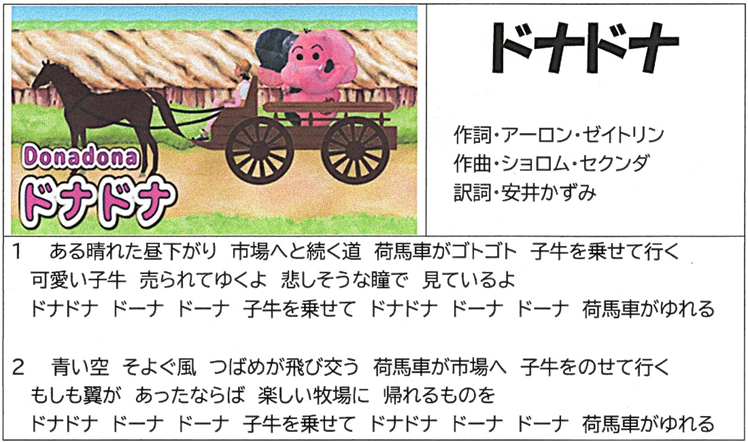
「作文学校」での苦い思い出
私の初任校は,いわゆる「作文学校」と呼ばれる,作文指導に力を入れている伝統校でした。私も学校中の熱心な作文指導にプレッシャーを感じながら,日々の実践に取り組んでいました。しかし正直なところ,まだ教師としての経験も浅く,作文指導にじっくりと腰を据えて取り組む余裕など,ほとんどありませんでした。

ある日,職員室前の廊下を歩いていると,作文審査に関する話が聞こえてきました。
「今年も作品が揃ったから,いけそうだね。〇〇君の学級はやっせんじゃろが,仕方なかね。」どうやら,私の学級の作品は期待されていないようで,内心穏やかでなかったことを覚えています。
そんな折,先輩の先生から「取材ノート」という方法を教えてもらいました。子どもたちに,自分が書いてみたいテーマを三つずつ挙げさせ,その題材に基づいて取材した内容を「導入・展開・終末」に分けて書き留めるノートでした。「友達との思い出」「おじいちゃんの仕事」「飼っている犬のこと」「母に叱られたこと」など,どれも子どもらしい題材ばかりでした。
その中から,子どもたちと対話を重ねながら,「自分にとっての事件性」や「忘れられない出来事と強く思ったこと」など,より深みのあるテーマへと絞り込んでいきました。そうしたやりとりを通して,少しずつですが,作品づくりの流れが形になっていく手応えを感じられるようになりました。 作文指導の研修では,ただ書かせた作品から推敲していくのではなく,「まず書きたくなる気持ち」を引き出すところから始まるのだと,学んでいました。

書きたくない気持ちに寄り添えずに
ある日,一人の女の子が「せり」という題材を取材ノートに書いてきました。兼業農家であるその子の家では,子牛を育てて市場に出していたのです。実はそれまでにいくつかのテーマを書いてはやり直しさせ,三回目に持ってきたのがこの「せり」でした。
「これは広がりそうだ!」私はそう直感し,ぜひこのテーマで書いてほしいと,その子にお願いしました。けれど,その子の表情は思ったより浮かないものでした。
「うーん,書きたくない」そう小さな声でつぶやいた子に対し,私は深く耳を傾けることなく,自分の判断を押しつけてしまいました。さらに,おじいさんにまで取材をお願いし,一緒に話を聞きに行ったのです。
「小さい頃から,子牛と一緒に遊んでいてな~」おじいさんが語ってくださった思い出話は温かく,心に響くものでした。私はそれをそのまま,作品の冒頭に取り入れさせようとしました。「出産のときに手伝ったこと」や「子牛と遊んだ楽しい日々」から作文の構成を考えたのです。
しかし,その子にとって,子牛との思い出は決して「楽しい」だけではなかったのです。教室で作文を清書させていると,ぽろぽろと涙をこぼし始めました。
子牛を市場に出す朝,自宅の牛舎の横でおじいさんが,「最後だから」と,言ってその子を呼んだそうです。子牛も何かを察していたのでしょう。トラックに乗せられ,角を曲がって見えなくなった後も,ずっと鳴いていた声が,耳から離れないと話してくれました。
あのとき私は,「書けそうなテーマ」にばかり目を向けてしまっていました。本当に書きたいこと,書きたくないことに,もっと心を寄せるべきだったのだと,今でも深く思い出します。

「書きたくない」と呟いていた
私はどこかで「感動的な作品を仕上げること」にばかり気を取られていたのです。結果として,その作文は郡の審査で入選しました。しかし,県の審査には進まず,その年の取組は終わりました。賞状を手渡したとき,その子は黙ったままで喜びの表情はありませんでした。
数日後,保護者の方からもお電話をいただきました。「家でも,辛かったことを思い出して,泣いていることもありました。今回の作文の書かせ方は,正直,良くなかったと思います。」
率直なご指摘に,私は返す言葉がありませんでした。そして深く後悔しました。私はただ,読み応えのある作文を書かせることばかり考えていたのです。結果として,子どもに深い傷を残してしまった。私の指導力の未熟さゆえの,忘れがたい経験となりました。
「作文学校の伝統を守らなければ」という思いが,私の中には確かにありました。けれど,それが先行しすぎて,肝心な「子どもの思い」に耳を傾ける姿勢を失っていたのです。どれだけ指導法や技術を駆使しても,子どもの心に寄り添えなければ,意味はないことを教えられました。