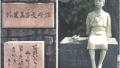私たちがよく観るNHKの「大河ドラマ」や「朝ドラ」は,史実を基にしつつも,多くの創作を加えられたフィクションです。「歴史小説」もまた同様で,史料だけでは描ききれない部分を,作家がさまざまな補助資料を基に,或いは創作して物語として形作っているのです。
よくよく考えてみると,ドラマなどで中世の武将たちが戦場で交わす長いセリフや雄弁なやりとりなどは史実なのか創作なのかはっきりしません。調べてみると実際の記録にはほとんど残っておらず,武将の書状に残る場合を除き,その多くが江戸時代に生まれた創作や講談,芝居などに由来するものだといいます。
それを踏まえて観ないと,ドラマや小説で描かれる人物像や会話のやり取りなどは,作者が創り上げた創作であるにも拘わらず,史実と思い込んでしまうことも多いようです。その一方,歴史ドラマと分かっていても,多くの作家がその人なりの人間観や歴史観に基づいて描いているので面白いのです。
朝ドラ「あんぱん」と「らんまん」
NHKの朝ドラは,全112作のうち,実在の人物をモデルにした作品が33作品あり,全体の約3割に当たります。また,私が朝ドラを録画して観るようになった90作目の『花子とアン』から『あんぱん』までの23作で,およそ65%に当たるようです。くしくも二つの作品は中園ミホさんの手によるもので,場面ごとに移り変わる繊細な人物描写が上手な脚本家です。
これらの点を踏まえると,ドラマや小説に登場する人物像や会話のやり取りが,たとえ創作であると理解していても,あたかも史実であるかのように受け取られてしまうことがあります。とはいえ,多くの作家がそれぞれの人間観や歴史観に基づいて描いているため,視点の違いが作品の多様性を生み出しており,そこにこそ作品の魅力や面白さがあるのも事実です。
また,そこに描かれた創作部分についても,ある程度の脚色は作品としての魅力を高めるための演出であると受け止められています。現在放送されている「あんぱん」での二人は新聞社で初めて出会っていますので,前半の幼馴染の設定はフィクションになるのです。しかし,二人の人物像や物語全体の流れに大きな隔たりがあるわけではなく,許容範囲の演出として楽しめました。

・NHKホームページより
ところが,二年前の「らんまん」には,やや複雑な思いを抱きました。主人公・槙野万太郎とその妻・寿恵子の人生が美しく,感動的に描かれていた一方で,史実と比べるとその人物像などあまりにもかけ離れており愕然とした記憶があります。

・NHKホームページより
実際には,ドラマで姉として描かれていた槙野綾の役割は,本来は万太郎の最初の妻・猶(佐久間由衣・役)なのです。しかも万太郎はその後,当時まだ十四歳だった小澤壽衛に一目惚れし,妻や親の承諾も得ないまま同棲を始め,翌年には長女が誕生しています。植物学者万太郎を描いた書籍等によると,遊女屋での浪費や,女中に手を出すといった逸話も残っており,私生活はかなり奔放であったようです。さらに妻の猶と番頭の井上和之助・竹雄(志尊淳・役)を結婚させて店の後始末をさせていたのです。
もちろん,彼の植物学における功績は疑いようのない素晴らしいものですし,研究にかける情熱は敬服に値します。しかし,それだけに,あまりにも美化されたドラマであったので,実像を考えると,何度か興ざめてしまいました。
史実とドラマの間には,どうしても埋めがたい隔たりがあるのは分かります。それでも,作品としての演出が過ぎると逆効果のような気がするのです。
歴史上の人物ランキング
話は変わりますが,学生時代から歴史のことで疑問に思っていたことがありました。たとえば,一剣豪に過ぎない「宮本武蔵」や一脱藩浪士の「坂本龍馬」といった人物が,どうして「戦国期や維新の三傑」より人気があり,ランキングで常に上位に名を連ねるのだろうか,ということです。
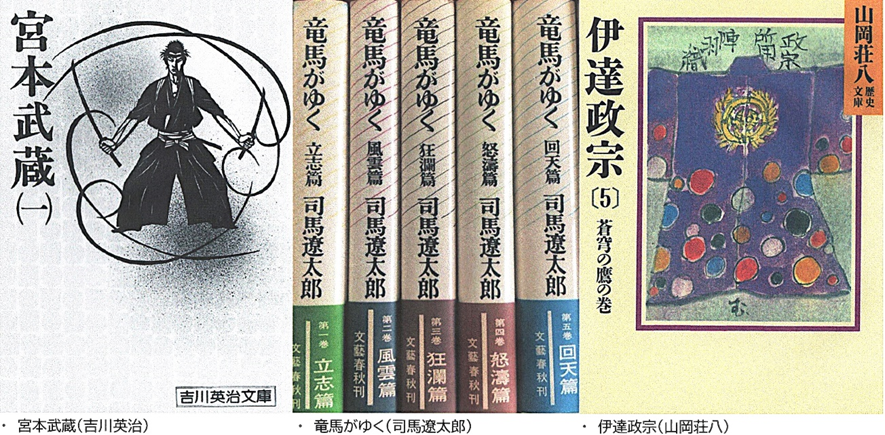
頼朝や義経,信長,秀吉,家康といった歴史の表舞台に立ったそうそうたる人物たちを押しのけてまで,彼らが人気を集めるのは一体なぜなのだろうと思っていました。歴史を語る上で,学問の位置まで達するには,多くの学者や歴史家に検証された根拠となる一次資料が必要です。
とりわけ坂本龍馬の人気は群を抜いていて,色々な人気調査で常に上位にランクインしており,例え維新の三傑ですら全く敵わないのです。西郷隆盛の10位や木戸孝允は62位,大久保利通は120位と引き離されています。小松帯刀をはじめとする「維新の十傑」に至っては,ランキングにすら出てこないのが現状です。帯刀がいなければ龍馬は歴史に登場すらしていなかったはずです。
一部書籍によっては,まるで龍馬が明治維新という大事業を,回りの獅子たちを取り込んで成し遂げたような印象さえ受ける描き方をしているものまであります。もちろん,「人気ランキングの投票」と言えばそれまでですが,その他の維新の獅子たちの評価が低くのは,少し気になるところです。
その大きな理由として,昭和30年代以降,龍馬を描いた歴史小説や映画,ドラマなどの影響が大きいと言われています。特に司馬遼太郎の作風は,読者に強い印象を与え,多くの人がその物語の人物像を新たな「史実」として受け止めてしまったようです。しかし,司馬遼太郎ご本人が「これは小説であり創作もある」と明言しているのに,作品の中の人物が独り歩きをしてしまったのです。
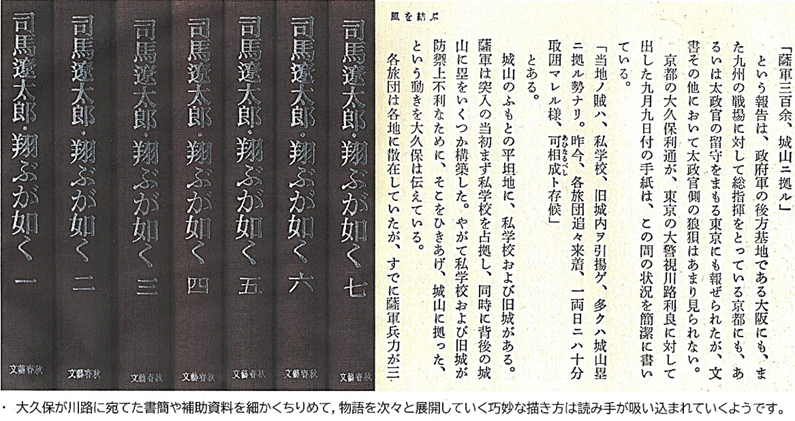
・司馬遼太郎の絶妙な描き方がよく分かる「翔ぶが如く」
このような背景には,歴史小説や大河ドラマが果たした影響が大きいと言われています。宮本武蔵を一躍有名にした吉川英治の『宮本武蔵』,坂本龍馬を国民的ヒーローへと押し上げた司馬遼太郎の『竜馬がゆく』,さらには山岡荘八の『伊達政宗』など,これらの作品は多くの読者の心をつかみ,その人物像を印象づけてきました。
朝ドラや大河ドラマ,そして歴史小説は,史実を土台にしながらも,作家の想像力と創作によって肉付けされた「物語」なのです。
足元を見据えた鹿児島の歴史観へ
| 鹿児島は島津氏とその一族が700年近く治めてきおり,支配者が大きく入れ替わることがなかった全国でも稀な地域ですので,支配者側の一次資料による偏った歴史観には注意が必要です。支配者が変わるとそれまでの正義や価値観が大きく変わることが多く,一方だけの資料に頼ると,全体を見失うことになりかねません。 また,鹿児島では国宝「島津家文書」が圧倒的な権威を占めているため,島津家文書の解釈研究で歴史が終わっているような気さえしています。敵対していた武将や大隅や奄美をはじめ地方史の資料は信憑性に欠けると,これまで活用されていない傾向が強いようです。これでは敗者の声や支配されてきた農民層の生き生きとした姿が多面的に描かれず,歴史観全体が面白みに欠け,全体像を見誤る可能性もあるのではないでしょうか。 『古事記』や『日本書紀』に記された神話の物語であっても,古来より全国各地で独自に育まれてきた歴史や神話伝承こそが,「日本の歴史」そのものを形作っているのです。鹿児島の歴史が島津家の歴史から抜け出せず,県内の足元(地方)を見ないことも課題ではないでしょうか。また,別の要因として明治維新や西南戦争によって分断された「薩摩人同士お互いを受け入れようとしない姿勢」にあったように思います。 歴史武将ランキングで薩摩武将が上位に上がらないのは,地方格差ということだけでなく,その実力や実績以外の要因があるようです。薩摩という厳しい地に多くの民衆が確かに生きていた,その歴史を統治者側からだけみると,読み手を虜にするような面白さに欠けているのです。この点が変わらなければ,大河ドラマに「島津義弘」や「島津三兄弟」が登場するようなことはないのでしょう。 |