 地名散策(23)
地名散策(23) 久しぶりの遠出~佐賀
良心的で妥当な宿泊費・ 佐賀駅構内 中国人観光団体客のキャンセルが相次いでいるというニュースを耳にし,久しぶりに夫婦で遠出をしました。何よりありがたかったのは,同じビジネス系のホテルで一日の宿泊費が二人で六千円と,前回の半分以下に抑えられた...
 地名散策(23)
地名散策(23)  地名散策(23)
地名散策(23)  地名散策(23)
地名散策(23)  地名散策(23)
地名散策(23)  地名散策(23)
地名散策(23)  地名散策(23)
地名散策(23) 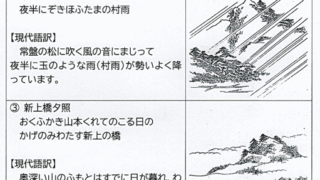 地名散策(23)
地名散策(23)  地名散策(23)
地名散策(23)  地名散策(23)
地名散策(23) 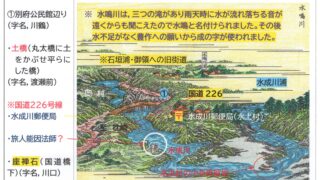 地名散策(23)
地名散策(23)