 歴史・自然(151)
歴史・自然(151) 「竜馬がゆく」と「宮本武蔵」等は創作小説
歴史資料等の典拠の必要性 郷土史を調べる中で,典拠や裏取りを含め関連する資料集めは大変です。主に県立図書館などで,必要な箇所をコピーしたり,ノートに写し取ったりしていますがそれにも限界があり,次第に史料そのものが欲しくなります。これまでも何...
 歴史・自然(151)
歴史・自然(151)  歴史・自然(151)
歴史・自然(151)  歴史・自然(151)
歴史・自然(151)  歴史・自然(151)
歴史・自然(151) 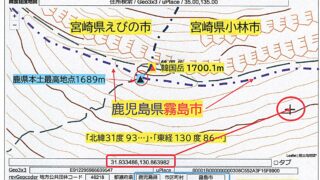 歴史・自然(151)
歴史・自然(151)  歴史・自然(151)
歴史・自然(151)  歴史・自然(151)
歴史・自然(151)  歴史・自然(151)
歴史・自然(151)  歴史・自然(151)
歴史・自然(151)  歴史・自然(151)
歴史・自然(151)